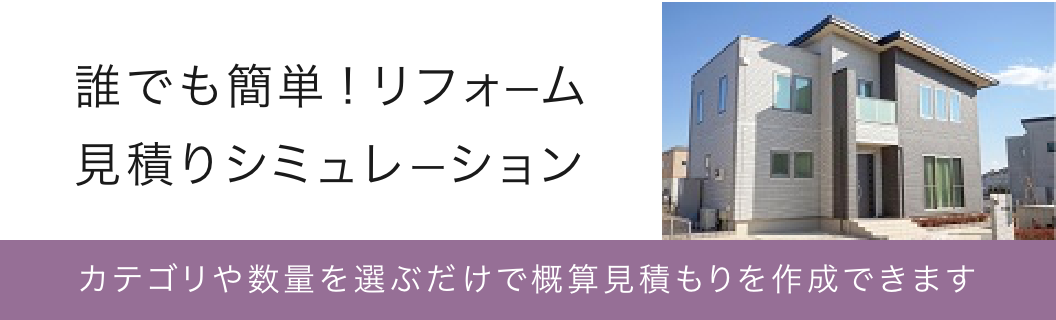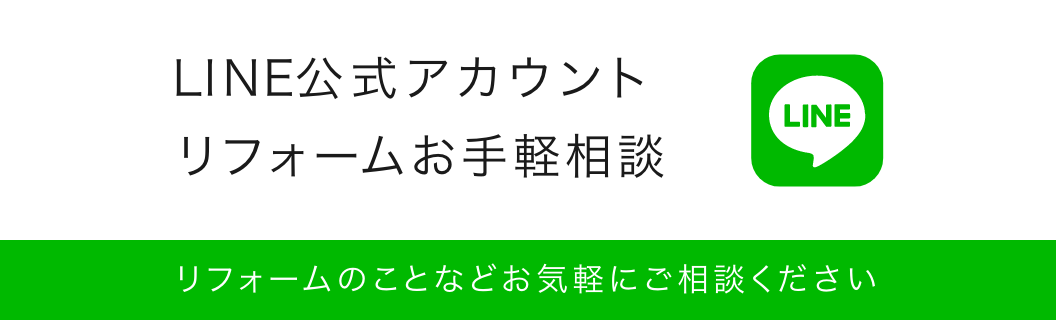タイルについて
皆さんこんにちは、建築部の富田です。
今回は、タイルについて掲載します。

↑浴室タイル張り状況
まずタイルとは、内外装の床や壁の仕上げに用いられる陶磁器製の建築材料の事で、石や粘土などを合わせた素地を高温で焼き上げた板状の資材です。
主にお風呂場の床や壁などの水回りや外壁などにもよく使用されているので皆さんも一度は見たことがあると思います。
タイルの語源はラテン語のtegula(テグラ)からきているそうで、tegulaは「物を覆う」という意味があります。日本では元々「敷瓦」「陶板」「貼り付け化粧瓦」などと呼ばれていましたが、大正11年に「タイル」という呼び名に統一されたようです。
タイルは色々な区分方法があり、そのうちの1つとして釉薬(ゆうやく)の有無によって「施釉タイル」と「無釉タイル」に分けることができます。
そもそも釉薬というのは、陶磁器の表面をコーティングしているガラス質の事で
釉薬を塗っているタイルを施釉タイル、塗っていないタイルを無釉タイルといいます。
無釉タイルが素地そのものの色になるのに対して、施釉タイルは釉薬がタイルの色を作るので色のバリエーションは豊富です。また、釉薬は光沢や味わいを出すほか、コーティングすることで防水性や強度が上がり、汚れにくくなるといった優れた実用性を兼ね備えています。


↑施釉タイル ↑無釉タイル
その他にもタイルは材質や吸水率などによってそれぞれ「Ⅰ類(磁器質タイル)」「Ⅱ類(せっ器質タイル)」「Ⅲ類(陶器質タイル)」に分類することができます。
・Ⅰ類(磁器質タイル)

石英や長石を1250℃以上で焼き上げて作られるタイルの事です。
吸水率が3%以下で、ほとんど水を吸わないので水回りに使うことが可能です。
耐久性に優れていて、汚れにくいという特徴もあるので、内装・外装・床・などあらゆる場所で使えるタイルです。
・Ⅱ類(せっ器質タイル)

粘土や長石などを1200℃前後で焼成したタイルの事です。
吸水率が10%以下で、磁器質タイルに比べると若干吸水率は高いですが、硬く、耐候性があります。
外壁に多用され、素朴な味わいのあるタイルです。
・Ⅲ類(陶器質タイル)

陶土や石灰などを1000℃以上で焼いたタイルの事です。
多孔質(細かい穴がたくさん空いている構造)なので吸水しやすく、吸水率も50%以下と高くなっています。
耐久性も他2つよりは低いので基本的には内装タイルとして使用します。
ちなみにですが、上の3つは元々そのまま「磁器質タイル」「せっ器質タイル」「陶器質タイル」と区分されており、それぞれの吸水率も
磁器質タイル →1%以下
せっ器質タイル →5%以下
陶器質タイル →22%以下
と、異なるものでしたが、2008年のJIS改正によって測定方法は自然吸水から強制吸水(煮沸法または真空法)に変更になり、
磁器質・せっ器質などの呼び名からⅠ~Ⅲ類という呼び名に変わりました。
区別方法などは若干違いますが、
「磁器質タイル」→「Ⅰ類」
「せっ器質タイル」→「Ⅱ類」
「陶器質タイル」→「Ⅲ類」
にほぼ該当するようです。
今回はここまで。
以上、建築部の富田でした。
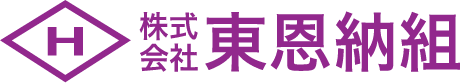
























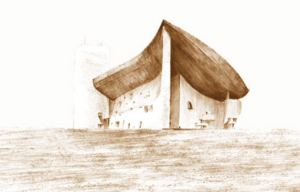


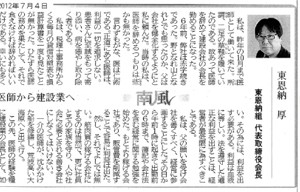











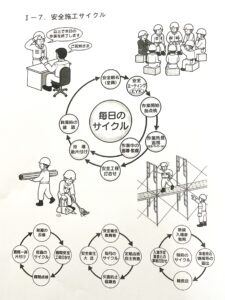



 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム