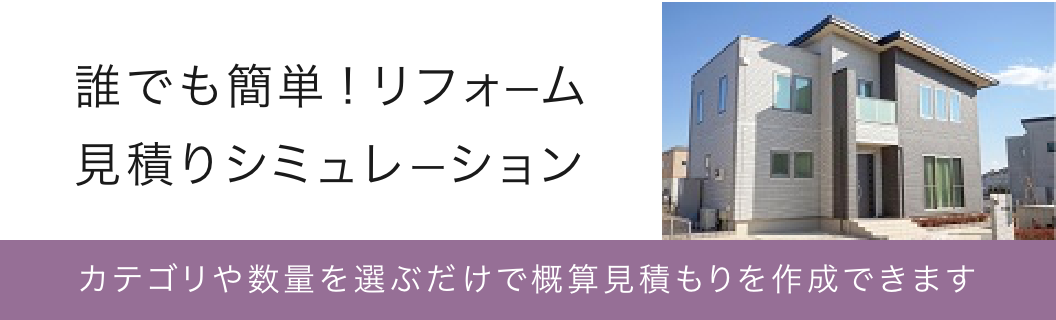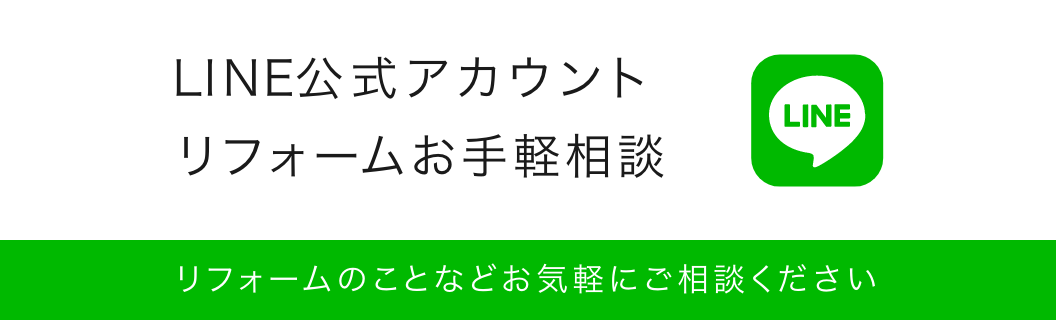用途地域について
お疲れ様です。
東恩納組建築部の又吉です。
今回は、用途地域について書いていきたいと思います。
用途地域とは、都市計画法の地域地区の一つで、用途の混在を防ぐもので、第一種低層住居専用地域など13種類があります。
なお、用途地域による用途の制限に関する規制は、主に建築基準法の規定によります。
都市計画法に基づき、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建物の種類、建蔽率、容積率、高さ制限などが決定することができます。
また、用途地域の指定のない区域などがあります。
こちらは、容積率などの制限を地方自治体が定める事ができます。
現在、用途地域としては、13種類あり、「8つの住居系」、「2つの商業系」、「3つの工業系」に分かれています。
今回は、「8つの住居系」を書いていきたいと思います。
1つ目は、第一種低層住居専用地域です。
高さ10mまたは12mまでの低層住宅しか建築できません。
コンビニなどの商業施設は原則として建築できませんが、生活に欠かせない施設は建築可能です。
基本的に閑静な住宅街であり、広い庭を持つ戸建てや、駐車場を作りやすい点がメリットの一つです。
2つ目は、第二種低層住居専用地域です。
こちらは、第一種の建設できる建物に加えてコンビニや飲食店などが建てられるようになっています。

3つ目は、第一種中高層住居専用地域です。
低層住居専用地域と異なり、高さ制限がなくなるため、分譲マンションが多く建ち並びます。
4つ目は、第二種中高層住居専用地域です。
第二種地域は、店舗建設が1500平方メートルまで認められています。
これにより、スーパーマーケットが建設可能となり、生活の利便性が大幅に向上することが期待されます。

5つ目は、第一種住居地域です。
主に住居が中心となっていますが、比較的大規模な建物の建設も認められており、商業エリアとしても利用可能です。
床面積3000平方メートルまでの店舗や事務所、宿泊施設も立てられます。ボウリング場なども立てられますが、カラオケ店等は原則建てられません。

6つ目は、第二種住居地域です。
第二種住居地域では、第一種に建てられる建物に加えて、カラオケ店等の娯楽施設も建設可能です。
7つ目は、準住居地域です。
準住居地域は、自動車関連施設と住居環境の調和を図るために、定められた用途地域です。
主に国道や幹線道路沿いのエリアが指定されています。
8つ目は、田園住居地域です。
2018年4月1日から新たに施行された田園住居地域は、低層住居専用地域と同等の厳しい建築制限が設けられた地域です。
この地域では、低層住宅を中心に農地と住宅街が共存しています。
用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
以上で終わりたいと思います。
建築部の又吉でした。
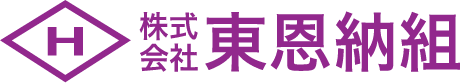
























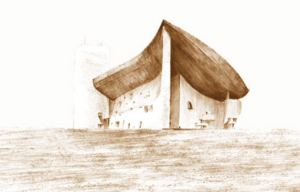


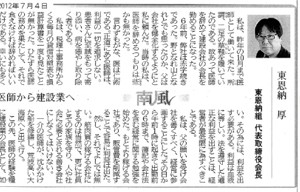















 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム