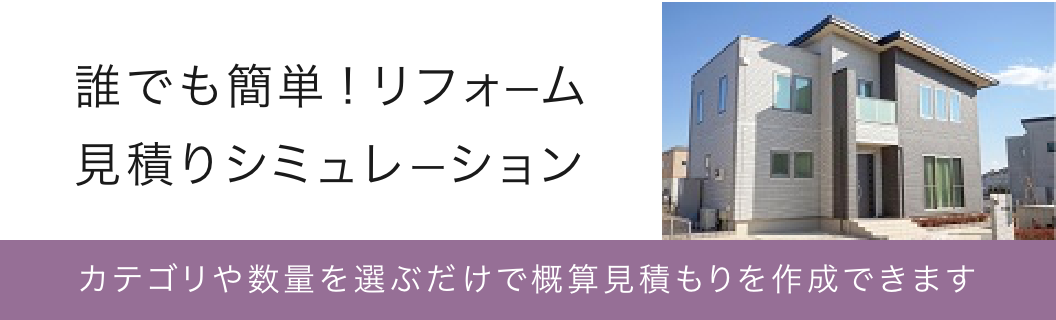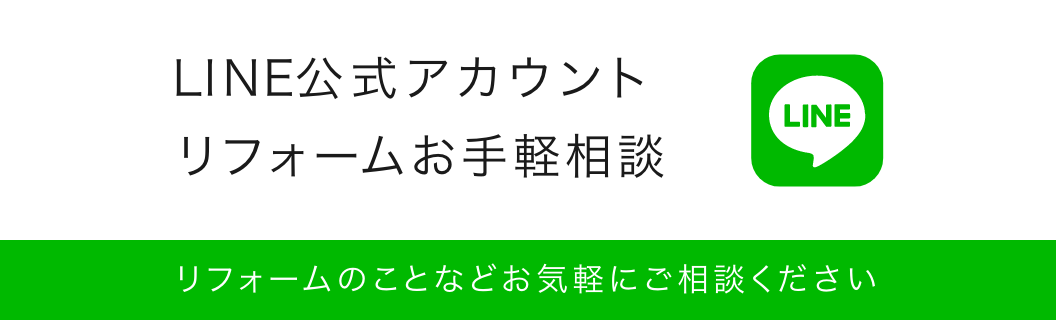北谷1丁目マンション計画新築工事より
皆さんこんにちは。建築部の大城です。
配属されている北谷1丁目マンション計画新築工事では、11月29日の2階躯体打設に向けて工事を進めています。

今回はコンクリートの豆板(ジャンカ)、コールドジョイントについてお話したいと思います。
コンクリート打設時に不備が生じると、豆板(ジャンカ)やコールドジョイントといった不具合が発生する可能性があります。
「豆板(ジャンカ)」とは、コンクリート打設後、コンクリートの表面が以下の状態の事を指します。
・骨材(砂利)が表面に露出する。
・モルタルが不足し、表面がザラザラになる。
・表面に空隙や巣穴のようなへこみが生じる。 等
豆板(ジャンカ)は構造体の強度低下や耐力低下を招く原因となります。また、「あばた」とも呼ばれますが、天然痘の瘢痕を指す為、差別用語なので使わないようにしましょう。

※参考写真
「コールドジョイント」とは、コンクリートを打ち重ねる際、先後のコンクリートが一体化せず、打ち重ね部に境界が生じる事を指します。流動性があるうちにコンクリートを打ち重ねることにより、先後のコンクリートが一体化、強固な構造となりますが、先行で打設したコンクリートが硬化し始めた状態で、次のコンクリートを打設すると一体化せず、打ち重ねの境界が残り、強度低下や水密性低下の原因となります。

※参考写真
●豆板(ジャンカ)の発生原因、対策
①型枠内での材料分離の発生
・コンクリートの横流しは行わない!
→モルタルは流動性があるが、骨材は流動性が無い為その場で沈み、分離しようとします。水平方向に移動させる距離が長いほど分離しやすい為、型枠内でのコンクリートの横流しは行ってはいけません。
・コンクリートの打込み高さは1m以下で行う。(標準は1.5m以下)
→高い所からコンクリートを打ち込むと、空中で材料分離が発生してしまう為、なるべく筒先は低く行う。
・コンクリートシュートを使用する際は、角度を30度以上で使用する。
→シュートの勾配が緩いと骨材は流れず、流動性があるモルタルが流れていく為、材料分離の原因となる。
②コンクリート振動棒の不適切な使用による締固め不足
・加振時間は5~15秒程度。50~60cm間隔で挿入する。
・打ち重ねる際は下層コンクリートに10cm程度挿入する。
・骨材を下げ、表面にセメントペーストが浮き上がり、気泡が少なくなる程度行う。
③コンクリートの充填確認不足
→打設中、上部では目視やバイブレータ、突き棒等を使用し、コンクリートが十分に充填されているか確認する。また、柱や梁の打設時に、鉄筋上にやむを得ずコンクリートが掛かる場合は、バイブレータでしっかりと落とす。
④型枠の叩き、締固め不足
→打設中、下部では型枠を小槌で叩いたり、壁用バイブレータを使用し、型枠表面の空隙を減らし、密実に締め固める。
●コールドジョイントの発生原因、対策
①コンクリートの打ち重ね可能時間を超えてしまった。
→タイムキーパー係等を設け、打ち重ね時間の管理徹底を行う。
※打ち重ね可能時間 気温25℃以上は120分以内、気温25℃未満は150分以内。
※練り混ぜから打込みまで 気温25℃以上は90分以内、気温25℃未満は120分以内。
②高気温時はコンクリートの硬化が早い
→高温時は打ち重ね時間内でも硬化が早まる恐れがある為、突き棒等を使用し、先行コンクリートの硬化状況の確認を適度に行う。
③打設順序などの事前計画が甘い
→筒先担当者は打ち重ね個所への戻り時間等に注意し、打設範囲を広げ過ぎないようにする。
→生コン車の待機時間を出来るだけ少なくし、良好なワーカビリティの状態のままコンクリートを打ち終える。
→渋滞する時間帯を考慮し、生コン車が遅延しないようにする。また、遅延した場合は圧送ホース内の残コンを適宜排出し、打ち重ね時間を確保する。
④コンクリートの締固め不足
→コンクリート振動棒の適切な使用(下層コンクリートへ10cm挿入等)
→先行バイブやリバイブを行い、先後のコンクリートを十分に一体化させる。


事前に計画、対策を行い、密実なコンクリートを打設したいと思います。
今回は以上となります。ありがとうございました。
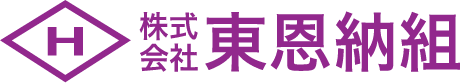
























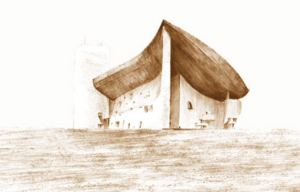


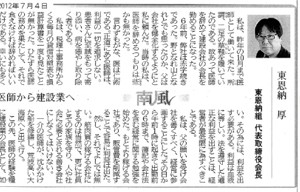















 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム